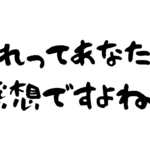あまりアクティブ運用を信じていません。思い返せば、ゴールドマン・サックスの株式商品が運用成績不調で強制償還になったことをきっかけに、アクティブ運用を辞めて早2年近くになります。(意外とそんな過去ではなかった。)
1960年代から1970年代にかけて、証券投資において「市場を予測することは困難」とする考え方が広まったことがきっかけで
「市場を予測するのではなく、受け入れる」
という概念のパッシブ運用が台頭してきました。これに対抗する形で、「市場には非効率性が存在し、それを突いて利益を得ることができる」と主張するアクティブ運用が発展しました。
パッシブ運用の理論的な基盤となっているのが、効率的市場仮説(Efficient Market Hypothesis, EMH)です。この理論は「市場にはすでにすべての情報が織り込まれており、誰も市場平均を継続的に上回ることはできない」とする考えです。1960年代にユージン・ファーマによって提唱され、この理論に従えば、銘柄を選んだり市場をタイミングで出入りすることには意味がなく、広く分散された市場全体を保有するのが最も合理的とされます。

「市場にはすでにすべての情報が織り込まれている」ということは、「合理的に動く全投資家を合計した行動」=「時価総額に比例した保有比率(つまり時価総額)」ということです。時価総額は、織り込まれたすべての情報をもとにその企業に対して市場がどれだけ価値を認めているかを示す数字(金額)であるため、まさにこの割合がリスクを最小化しながらリターンを得られる
最も合理的なポートフォリオ
ということになります。(リターンの最大化でないことに注意)
特に1980〜1990年代はアクティブ運用が全盛期を迎え、著名なファンドマネージャーが数々の成功例を生み出しました。ウォーレン・バフェットのように長期的な企業価値を重視したバリュー投資家は、その代表格とされています。しかし2000年代以降、アクティブファンドの多くが指数(ベンチマーク)に勝てないという実証結果が目立つようになり、ETF(上場投資信託)を中心としたパッシブ運用が人気を集めているのが現状です。
この
リターンの最大化ではなく投資効率最大化(リスク最適化)
という保守的な考えを受け入れてしまっているため「アクティブ運用を信じる人はどんな神経しているんだろ」と長年疑問に思っていました。しかし、最近一つの答えを見つけました。
「麻雀のプロに向いている人はどんな人か」という疑問に答える番組で、岡田紗佳プロが
「1000万円を10人で山分けして100万円取るのと、10人で勝負して1000万円を一人だけ取れる。どっちを選びますか?麻雀プロに向いているのは1000万円を取れると思う方なんですよ」
と回答していました。

投資理論を少しでも嗜んだ人ならば聞いたことがある「ゼロ・サム・ゲーム」の話そのものです。株や債券は配当や利息(キャピタルもそうですが)を複数人で分配することが出来るので「ゼロ・プラス・ゲーム」と呼ばれます。10人が10人、ハッピーになることができます。
一方でパッシブ運用(インデックス運用)を軸に考えると、ここで投資効率は理論上最大化されていますから、アクティブ運用はパッシブ運用の凸凹を取り合うわけですから
パッシブ運用対比の超過収益
という土俵においては「ゼロ・サム・ゲーム」(誰かが笑えば誰かが泣いている)になります。


草食系の私としては、皆でハッピーになればそれで満足していたので、ということに加え「数学的に最適」という言葉に魅力を感じてしまったので、このような肉食系の発想には至りませんでした。逆に言えば、このような肉食系の発想を持つのであれば
アクティブ運用が脳内で正当化される
ということが分かったのが感動でした。
さらに岡田プロは「たまにいるんですよ100万円を山分けしたい人。確かにそういう人は、丁寧にやるんですけど、いまいちパッとしない麻雀プロが多いんですよ。勝ちきれないと言うか。優勝するには勝負しなきゃいけないのに、それができない麻雀プロが100万円を取る人が多い」ということで、まさにパッシブ信者である私と、まるでアクティブ・ファンドマネージャーそのもののような回答していました。
やっぱり私はアクティブ運用は辞めておいた方がいいということを再認識しました。