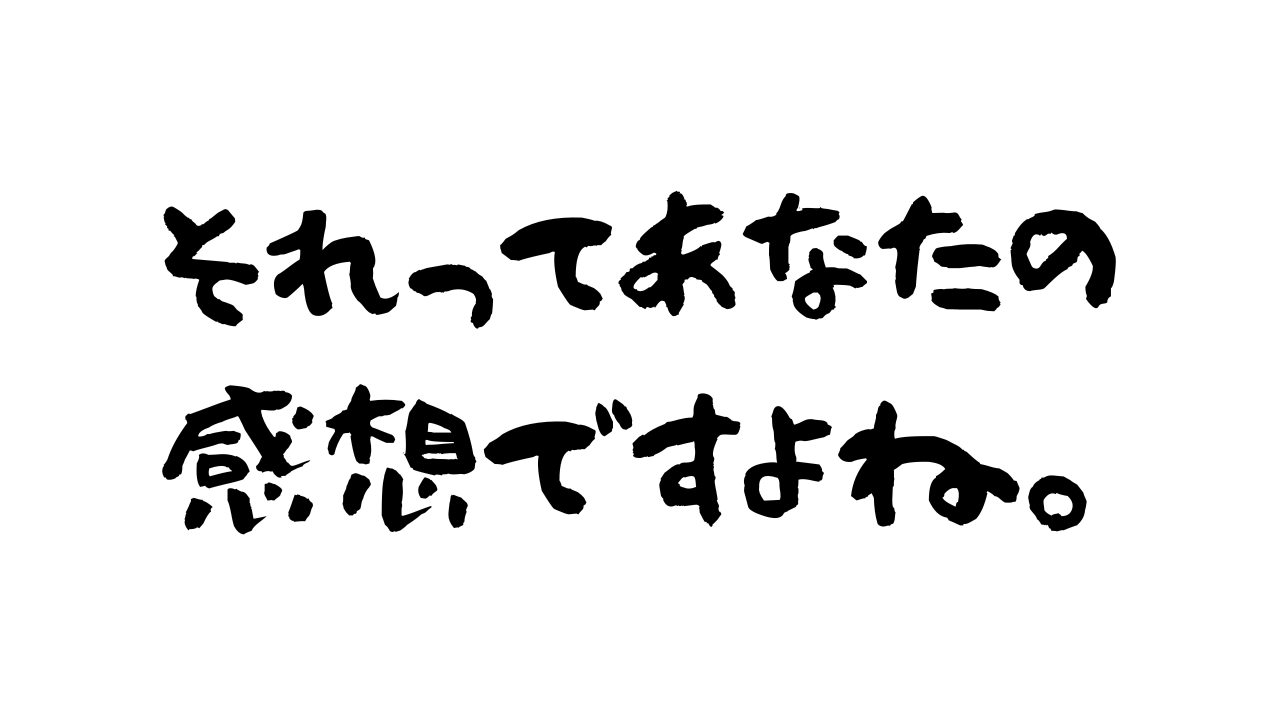「まともな理系大学は卒業するまでに、論文、統計、実験とかで、実証されたものを事実とみなす訓練をするんだけど、仕組みが理解出来ないから、人を信じるしかないんだろうね、、、文系の害はこういう所にもある」と、ひろゆきこと西村博之氏が呟いていることがyahooニュースになっていました。

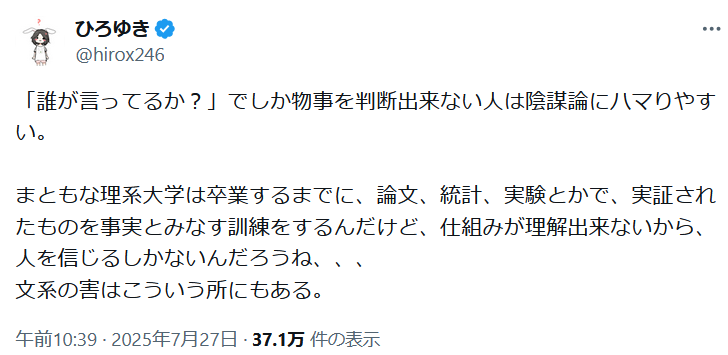
コメント欄でも「理系が優れているばかりではない」とあるとおり、全てにおいて理系が優れているということに同意するつもりはないのですが、AIも発達して膨大に情報が世の中にあふれており、情報の選別にはある程度の理系的素養が必要になってきたと最近強く思うようになりました。
特に官公庁のデータだけでなく、Xやインスタ、YOUTUBEと様々なデータがあふれ、同時にデータへのアクセスが容易になったため、何事でも「N=1」(何かしらサンプルがある)状態は当たり前になってきました。
具体的には仕事でも「この場合どういう事例があるのか?」とかプライベートでも「これについてどう思う?」と他愛もない会話になったときに
そのようなデータはない
ということに出くわすことがなくなり、スタート地点で何かしらバイアスがかかった状態で議論を開始することが多くなりました。昔は「データがないのならば何かしら理論を積みあげよう」というゼロベースから始めることが多く(ほんの5年目まで情報は紙ベースでしたから)、まずは教科書等の「みんなが知っていること」から始まるため、初手で180度異なる議論が存在したり、勘違いのまま議論が進んでいくことは稀だったように思います。
今では当たり前に海外の論文にアクセスでき、当たり前にAIが翻訳してくれるの、テキストレベルでの海外の情報格差は10分の1になったように思えます。「ちゃんと翻訳できているの?」とか「ちゃんと理解して物申してる?」という懐疑心が昔はありましたが、今ではgoogle翻訳でもとてもしっかりしていますし、内容についてはAIに「概要を教えて」と入力すれば複数のAIで比較して、その真偽を相対的に判断できるようになりました。
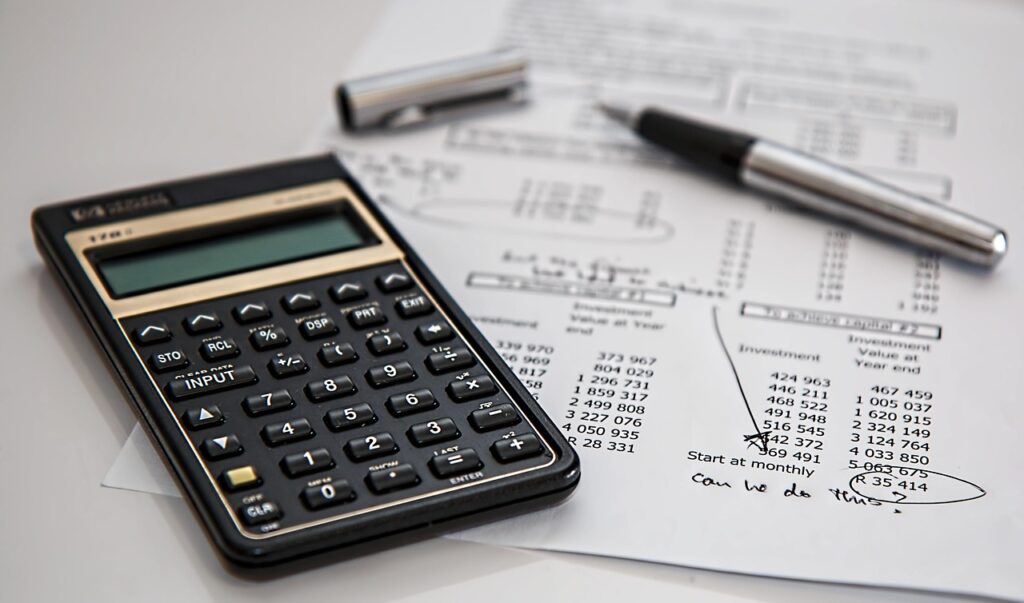
加えてインスタやYOUTUBEも専門家がコメントしていたりするので、一昔のように
なんか素人が言っているよ
と無下にできなくなってきました。結果的に「データを集める」ということよりも、「何が信頼できるデータソースか(もしかしたら全部信頼できるかも)」という判断を下すことが重要になってきたかと思います。
個人的に危機感を覚えたのは、「少量のアルコールは体に良い」という説が間違いだったということを知ったときです。小さいときからなんとなく「酒は百薬の長」と並んで頭に刷り込まれた常識でした。情報を遡ると2018年8月23日に世界的権威のある医学雑誌ランセットに掲載された論文のようです。
統計的なミスがデータには含まれていて、そもそも「健康状態が良くない人は酒を飲まない」というサンプルが含まれており、「多少酒を飲んでいる集団のほうが健康状態が良い」という誤解を生んでしまいました。

このように「母集団(抽出)は適正なのか」「ランダム性(偶然性)を含んでいないか」「変なバイアスが残っていないか」ということを数字を使わず(それこそ正規分布や標準偏差と言った数学的素養なしに)判断することや、言語として他人と議論することは難しいように思えます。
また、こういったデータ分析の場でなくても、理系と文系の差を感じることが多いです。
何気なく言語として出てくる「たくさん」とか「少ない」という定量的な部分はもちろん、「とても」や「あまり〇〇ない」という修飾語?副詞?もやはり数字的な感覚は必要です。私も仕事で部下のような人たちができて来まして、ほぼ文系出身で構成されています。会議や何気ないディスカッションで「とても」とか「多い」という日本語を使われると、数秒後には「何を判断基準にその言葉を使っているのか?」と突っ込んでしまうことが良くあります。
回答は「何気なく使ってました。」というもので、もちろん多少主観が混じることは否定しないのですが、「20%上昇を”たくさん”と表現している」「〇〇と比較して発生頻度が多いことを”多い”と判断した」という回答は持ってもらいたいです。週に3回カレーを食べたら日本人は「多いな」と感じるでしょうか、きっとインド人は「少ない」と感じるはずです。このように定量的でない言語で議論されてしまうと、むしろコミュニケーションの妨げになってしまうと考えていますし、このように主観的な言葉が多い人は、物事の本質を捉えていなかったり、やっぱり思考が浅いまま進めているようなことが多いので、一緒に仕事するときは警戒するほどです。

この「定量的に語ることができない」ことの最大の問題は
リスク(不確実性)
を議論するときに生じます。アクチュアリーの人はリスク(不確実性)を表現するための道具をたくさん持っていますが、普通の人、特にあまり数学的教育を受けていない人とにっては
リスクが「ある」か「ない」
で判断することになってしまっています。「道具」という意味でよく使う指標は「期待値」や「標準偏差」のように、リスクの大きさやリスクのトレードオフに存在するリターンも絡んだ議論を行うための”共通言語”を持って他人に伝えることができます。これに加え「ポアソン分布」や「対数正規分布」というように、その事象がどんな属性でかつどんな前提条件で発生するのか(=分布)と言ったなかなか日本語では表現できない情報を瞬時に伝えることができます。
きもいですが。
アクチュアリーとしてはこういった表現方法を知らない人と議論するとなると、幼稚園生(なんたって「ある」「ない」しか言えないし、数字も「0」と「1」しか知らない)と業務内容のコミュニケーションを行うことと同義になるので、非常に疲れます。もちろん遊びならばいくらでもいいですが、幼稚園生と議論して業務として答えをださなくちゃいけませんので。

よくある場面としては、と事例を出したいところですが、もうそれはどんな場面でもあり得ます。
そもそもビジネスに何事もリスクが存在します。逆に言えばリスクが存在しないビジネスは「誰でも何も損をせずに儲かるビジネス」であって、逆に参入しないわけがありません。(だから存在しないという逆説ですが。)また、資本主義の原理が「リスクを取る者がリターンを得る(ことがある)」というものなので、リスクがないものはリターンがないことになります。
ですがすぐに「リスクがあるから辞めよう」という議論になりがちですし、普通のサラリーマン(従業員)だけでなく経営側でも同様の発言をする人が多くいます。
なかなかリスクを定量的に比較することが難しいです。その裏にあるリターンも比較しつつ議論することはなかなか「危ない」「儲かりそう」「うまくいけば」という日本語だけでは難しいように思います。例えば、100円を参加料として1万円が五分五分で貰える(貰えない確率が50%ある)というゲームがあった場合に、「リスクがあるから危ない」と参加を見送るのでしょうか。
数学的に言えば期待値は4900円(1万円×50%-100円)なので、圧倒的に参加料は安く
参加しないわけがない
と判断できるゲームと言えます。
ビジネスだけでなく、資産運用もそうですし、マンション価格の高騰が止まらない昨今の不動産投資もそうですね。結果論ではありますが。昨年のMEGABIG騒動も、こういった知識を持ち合わせた人たちの戯れだったのかと思います。
理系側の人間として、日頃感じることを綴ってみました。